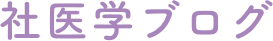理学療法学科夜間部2002年3月卒業
武蔵野中央病院 リハビリテーション科 勤務
細井 匠 先生
2002年3月に理学療法学科夜間部を卒業し、現在は武蔵野中央病院でリハビリテーション科の科長を務められている細井匠先生。
学生時代はボクシングに夢中になり、一冊の本との出会いから大学卒業後に理学療法士を目指し、社医学に入学。昼は病院で働きながら夜は学校に通うという忙しい学生時代を過ごしましたが、その経験が今の充実した仕事につながっています。
そんな細井先生に、現在の仕事の事、社医学での学生時代の事などお話を伺いました。
〜働きやすい環境を作ることも大事な仕事〜
Q:本日はよろしくお願いいたします。細井先生はこちらの病院(武蔵野中央病院)に社医学卒業後からずっと勤務されていらっしゃるのですね。
もう23年ぐらいですね。今はリハビリテーション科の科長をしています。ここは精神科と内科の病棟があり、精神疾患に身体疾患を合併した方への理学療法業務を中心に行っています。
その他、理学療法士1年目から研究発表をさせてもらう機会があり、そのまま臨床と並行して研究活動をしていたおかげで、臨床8年目には専門理学療法士というものになり、学会の演題査読や座長、論文の査読や研修会の講師を依頼されることがあります。
また、日本精神・心理領域理学療法学会の理事としての活動や、市内のセラピストの会での役員としての活動、東京都や市の介護予防事業に関する活動があり、様々な分野の方と関わる機会が増えています。あとは、臨床実習生の指導も年間7~8名は行います。
Q:かなり多方面でご活躍されていますね。こちらの病院では、リハ科のスタッフの皆様が、とても良い雰囲気の中で仕事をされていらっしゃるように感じました。
そう言った雰囲気を作るのは、仕事を続ける上では一番大事な事ですので。みんな仲良くやっていると思います。
〜人生を変えた、何気なく手に取った本との出会い〜
Q:素敵な職場ですね。細井先生の趣味や特技、お休みの日の過ごし方などを教えていただけますか?
高校大学とアマチュアボクシングをずっとやっていたので、今でもボクシングを中心に格闘技全般、観るのもやるのも大好きで、休みの日はトレーニングしています。
社医学時代の同期で,現在は社医学で教鞭をとる小宮山先生の影響で始めたサーフィンも好きで、行く頻度は随分と減りましたが、今でも続けています。
それと、長年バイクに乗っているのも趣味といえば趣味かもしれません。その他にも読書、漫画、映画、ドラマなど常に何かしらを楽しんでいます。
Q:かなり多趣味でいらっしゃいますね。
常に忙しくしている方が性に合っているので、何もしていない時間は無いと思います。
趣味とは違いますが、社医学時代に昼間仕事をしながら夜学校に通うという事を当たり前にやっていたので、社医学卒業後も大学院に進んで修士課程・博士課程と学ぶことができました。やっているときは大変なのですが、それが終わると物足りなくなってしまうので。

Q:すごく勉強熱心ですね。
一時は作業療法士の資格も取得しようかと考えることもあったぐらいです。さすがにそれはやめましたが(笑)
Q:それはすごいですね。では、細井先生が理学療法士を目指したきっかけを教えていただけますか?
中学生の頃からボクシングをやりたくて、ボクシング部のある高校を探して進学し、アマチュアボクシングを始めました。その後、スポーツ推薦で大学に進学したのでずっとボクシング漬けの日々でした。
1990年代半ば、バブル崩壊後の就職氷河期と言われる時期です。ボクシングを生業として続ける事に限界を感じて、かといって他にやりたい仕事も就職先も無く、漠然とした閉塞感に苛まれ、将来進む方向に悩んでいました。
そんな頃、書店で何気なく手に取った「理学療法士・作業療法士になるために」というようなタイトルの本を読んで、「運動の知識を活かせそうだし、何だか面白そうな仕事だな」と感じたのがきっかけです。
Q:手に取った本がきっかけとは、面白いですね。
当時は今のようにネット通販は無かったですし、よく本屋に立ち寄っていたのですが、本当に「なんとなく」手に取りました。
Q:それはすごい運命的な出会いですね。それからすぐに理学療法士を目指して社医学に進学したのですか?
手に職をつけたいという考えがあって、「理学療法士になるには専門学校を出る必要がある」ということは理解していたのですが、「専門学校なんて小論文でも書けば誰でも入れるだろう」と甘く考えていました。
当時は養成校も少なく、大学4年生の時に数校受験しましたが不合格となってしまい、就職活動もしていなかったので無職になりました。
なので、それからアルバイトをしながら中学1年生の勉強からやり直し、翌年社医学に合格することが出来ました。
Q:1年間の勉強期間を経て入学されたのですね。では社医学の夜間部を選んだ理由は何ですか?
実家から近くて通いやすかったことと、大学まで出してもらったのに、これ以上両親に金銭的負担をかけるのは忍びなく、「昼間は働ける方が良い」というのが理由です。
〜楽しくて充実した時間を過ごした社医学時代〜
Q:社医学時代はどんな学生生活を送っていましたか?
昼間は高齢者が長期に入院している病院で3年間勤務しました。そこでは患者さんから多くのことを学ばせてもらえたので、学生としてはありがたい環境でもありました。4年生の時、長期臨床実習に行くために退職しました。
夜は週5日社医学で授業を受け、授業が終わる21時過ぎからは、週に1回ずつ、異種格闘技とフットサルのサークルに参加していました。
また、勉強が得意な方ではないことを自覚していたので、入学後も人一倍努力をしないと皆について行けないと思い、サークルの無い日は残って復習をしていました。でも努力の割に成績は今一つで、よく追試験を受けていましたね。
今、思い返すと凄く忙しかったような気もしますが、とても充実した、楽しい時間を過ごせていたと思います。
Q:勉強が得意ではなかった先生が、当時行っていた勉強法などはありますか?
私は「ダブルノート」をつけていました。授業でノートをとるのですが、それを学校に残ってもう1回ノートにまとめることで、頭の整理をしていました。
Q:勉強熱心な先生の性格が表れていますね。社医学で思い出に残っているエピソードはありますか?
当時、仲の良い同期とは大抵ふざけた話をしていました。また、試験や実習などのイベントがある毎に打ち上げがあり、よくクラスメイトとお酒を飲んでいたことを覚えています。
後は、臨床実習が思い出深いですね。学院がレオパレスを借りてくれ、神奈川県の遠隔地で2ヶ月間の実習に行ったのですが、当時はサーフィンを始めたばかりで、「神奈川なら海に近い!」と思って喜んで行きました。
実際には海まで結構な距離がありましたが、土日は休みの病院でしたので自転車で1時間ほどかけて海に行って波乗りをしていました。休み明けの月曜日に実習地に行くと、指導者から「また日焼けしてる!」と怒られていました。(笑)
今でも湘南に波乗りに行くと、当時自転車で通った道を車で走る事があり、あの頃の事を思い出しますね。

〜社医学で4年間過ごして理学療法士になることが出来て本当に良かった〜
Q:それは今だから話せる内容かもしれませんね(笑)先生が理学療法士として現場で働いていて、社医学で良かったと思う事はありますか?
あちらこちらに先輩・同期・後輩がいて、良かったと思うことは多々あります。
実は学生時代に勤務していた病院に、非常勤で来ていた理学療法士も社医学夜間部の大先輩で、普段の勉強や就職・進学の際にも大変お世話になりました。あれだけ面倒を見てくれたのは、やはり同じ学校の後輩という立場であったからだと思います。
それと、卒業後に出会った人たちと出身校の話になった時、だいたいほとんどの人は「社医学」を知っているというところも強みかもしれません。
Q:”卒業生ネットワークのひろさ”と”知名度”は、卒業生の皆さんが口を揃えて仰っています。
他にも、就職してからも現場で臨床業務をしながら、社会人向けの大学院で修士課程・博士課程と学ぶ事が出来たのですが、これも社医学夜間部での経験があったからこそだと思います。
働きながら勉強するので、忙しくなるのは分かっていましたが、「再び充実した時間が送れる」と思い、全く抵抗はありませんでしたし、「社医学で慣れているから大丈夫!」と思って仕事の後に通学し、楽しい院生生活を送れました。
Q:それでは最後に、理学療法士を目指している方、あるいは社医学を検討されている方にメッセージをお願いします。
理学療法士に限らず、対人援助職は様々な人生経験が活かせる仕事だと思います。他のお仕事をされていて、「理学療法士になろうかな?」と思う方がいたのなら、働きながら学べる社医学は良いと思います。
私は社医学で4年間過ごして理学療法士になることが出来て、本当に良かったと思っています。いろんな経験をすることができて非常に財産になりました。
夜間部での生活は忙しいとは思いますが、私自身は「暇」と「退屈」が大嫌いです。同じ漢字を使いますが,「楽(らく)」って「楽しい」とイコールではないと思うんです。
現場に出てから20年以上が経ちましたが、今でも忙しく、充実していて仕事全般が「楽しい」です。志を持って社医学夜間部に入学したら、きっと「楽しい」と思いますよ。
本日はありがとうございました。
インタビュー日:2025年3月